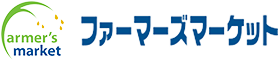2025年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられ、従業員40人以上の企業にも雇用義務が課されます。本記事では、違反時の罰則や企業名公表のリスク、行政指導の流れ、助成金などの支援制度まで詳しく解説。制度改正にどう備えるべきか、企業の実務担当者が押さえておくべきポイントをまとめました。
この記事を読むと分かること
- 障害者雇用率の引き上げ内容と対象企業は?
- 未達成の場合、罰則や企業名公表はあるのか?
- 企業はまず何から始めればよいのか?
- 活用できる助成金はあるのか?
2025年の障害者雇用義務化の最新動向
障害者雇用促進法の概要
障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)は、1960年に制定され、障害者がその能力と適性に応じて働き、社会参加を実現できるよう、雇用の確保・促進を企業に義務付ける法律です。事業主に対して一定割合以上の障害者を雇う「法定雇用率」の達成を命じるとともに、障害者に対する差別の禁止や、合理的配慮の提供義務も盛り込まれています。これにより、日本国内のすべての企業に対し、障害者雇用に主体的に取り組む責任が課されています。 参照:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律」
法定雇用率の推移と2025年の改定内容
2025年4月から、障害者の法定雇用率が引き上げられることが決定しています。現在(2024年6月時点)の民間企業における障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月より2.5%、そして2026年4月には2.7%へと段階的に引き上げられる予定です。これにより、障害者の雇用がさらに促進され、多様な人材活用が進むことが期待されています。
| 年度 | 民間企業 | 国・地方公共団体 | 都道府県等の教育委員会 | 対象となる企業 |
| 2023年度まで | 2.3% | 2.6% | 2.5% | 従業員43.5人以上 |
| 2024年4月~ | 2.5% | 2.8% | 2.7% | 従業員40人以上 |
| 2026年4月~ | 2.7% | 3.0% | 2.9% | 従業員37.5人以上 |
(参照:厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく 法定雇用率の引上げについて」)
法定雇用率の計算方法
法定雇用率は、常用労働者に対して障害者雇用者が占める割合です。計算方法は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 分子 | 雇用保険被保険者かつ障害者として雇用している人数 (重度障害者は1名につき2人、短時間労働者は0.5人換算など) |
| 分母 | 常用労働者数(雇用保険被保険者数など) |
| 算出式 | 障害者雇用者数 ÷ 常用労働者数 × 100 = 雇用率(%) |
「重度身体障害者」「重度知的障害者」は1人を2人分、「週所定労働時間20時間以上30時間未満」の短時間労働者は0.5人に換算されます。詳細な算入基準や計算方法については、厚生労働省の公式ページを参照してください。 (参照:厚生労働省「障害者雇用率制度の概要」)
雇用率計算に含まれる障害者の種類
法定雇用率の計算に含まれる障害者は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が対象となります。2018年4月からは「精神障害者」も法定雇用率の算定基礎に新たに加えられています。
| 障害の種類 | 算定基準 | 備考 |
| 身体障害者 | 含む | 重度の場合は2人分換算 |
| 知的障害者 | 含む | 重度の場合は2人分換算 |
| 精神障害者 | 含む | 2018年4月から対象 |
いずれの場合も、障害者手帳などで障害が確認できる必要があります。今後、雇用義務の強化により、精神障害者や発達障害者などへの配慮や、雇用管理体制の整備が一層求められます。 (参照:厚生労働省「障害者雇用率制度の概要」)
障害者雇用義務違反の罰則と行政指導
報告義務違反・未達成の場合のペナルティ
障害者雇用促進法にもとづき、一定規模以上の事業主(2024年4月現在は従業員43.5人以上)は、法律で定める障害者雇用率以上で障害者を雇用する義務があります。この「法定雇用率」が未達成の場合、以下のようなペナルティが科されることがあります。
| 違反内容 | 主な措置・ペナルティ | 根拠条文 |
| 雇用状況報告義務違反 | 報告命令、従わない場合は50万円以下の罰金 | 障害者雇用促進法第43条、第86条 |
| 法定雇用率未達成 | 障害者雇用納付金(1人不足ごとに月額5万円/2024年4月現在) 是正指導や計画書の提出指導 | 障害者雇用促進法第44条、第48~51条 |
障害者雇用の報告を怠るだけでも罰金対象となることがあり、また雇用率未達成が続いた場合は、厚生労働大臣から是正勧告がなされます。 参考:障害者雇用促進法に基づく事業主の皆様へのご案内|厚生労働省
ハローワーク・労働局による是正勧告や勧奨
法定雇用率未達成の企業に対して、ハローワーク(公共職業安定所)や労働局より以下のような指導・是正勧告が行われます。
- 障害者雇用に関する進捗や体制確認
- 「障害者雇入れ計画書」などの提出と実施報告の指導
- 障害者向け求人の積極的な発出や採用活動の実施要請
- 指導に従わない場合は「是正勧告」から「企業名公表」の措置へ進行
この段階では行政からの積極的な支援・アドバイスも並行して行われるため、指摘事項に対し着実に対応することが重要です。特に「改善指導書」や勧奨文書を受けた際は、遅滞なく具体的な対応をしなければなりません。 詳細:障害者の雇用の促進等に関する法律の概要|厚生労働省
企業名公表のリスク
厚生労働省は、「十分な指導を行っても法定雇用率を2年以上にわたり著しく下回り、かつ障害者雇入れに関する計画書を期限までに作成・実施しない企業」に対し、その企業名および違反内容を公表する措置を実施しています。いわゆる「企業名公表」は、企業の社会的信用の失墜やレピュテーションリスクとして多大な影響を及ぼします。企業名公表に至らないためにも、早期の是正と障害者雇用推進に積極的に取り組む必要があります。 参考:法定雇用率未達成の企業に対する企業名公表制度について|厚生労働省
【万が一の場合】企業名公表までの流れ
障害者雇用促進法に基づき、企業は法定雇用率を達成する義務があります。未達成が続いた場合、最終的に企業名が公表されることになりますが、そのプロセスは複数段階に分かれており、「いきなり公表」とはなりません。ここでは、万が一障害者雇用義務違反が続いた場合の企業名公表までの流れについて、詳しく解説します。
まず最初に:事前告知
法定雇用率未達成の企業に対しては、厚生労働省やハローワークから状況の報告や説明を求める「事前告知」が行われます。具体的には、障害者雇用状況報告の際、未達成が明白な場合に対して書面や電話での連絡により、「雇用率が達成されていない状況が把握された」と通知されます。 この段階では、改善意欲があるかどうか、雇用計画の有無を確認する意味合いが強く、働きかけを通じて自主的な改善が期待されています。
2年間の経過観察:「障害者の雇入れに関する計画書」の提出指導
改善が進まない場合、「障害者の雇入れに関する計画書」の提出を求められます。これは企業に対し、2年間を目安に障害者雇用率をどのように達成するか計画を策定・提出させ、ハローワークが進捗を定期的に確認するものです。計画期間中は雇用目標が達成できるかを定期的にチェックされ、計画が不十分な場合や進捗が芳しくない場合は、ハローワークや労働局による更なる指導が行われます。
猶予期間は9ヶ月:特別指導
2年間の計画期間を経てもなお雇用率が未達成の場合、原則としてさらに9ヶ月の猶予期間が与えられ、より厳しい「特別指導」に移行します。この間に求められるのは、具体的な採用活動や職場環境の改善など、実効性のある対策の実施です。 ハローワーク等の指導のもと、個別面談や求人活動の指導、就職面接会への参加義務化など、達成に向けた具体的な評価と対策が継続されます。
企業名公表
上記の計画期間・猶予期間を経ても、依然として法定雇用率が達成されていない場合や、正当な理由なく計画を履行しなかったとき、ついに企業名が厚生労働省から公表されます。 この企業名公表の事例は、毎年厚生労働省の公式サイトで公表され社会的なペナルティとなります。また、社会的信用低下や取引停止、人材採用への悪影響も懸念されるため、経営リスクとしても非常に大きなものです。 企業名公表を防ぐには、早期に指導や経過観察に真摯に対応し、障害者雇用の推進体制を整えることが重要です。なお、企業名公表は障害者雇用納付金制度による納付金徴収(1人当たり月額5万円、2024年4月からは5万5,000円以上)や、厚生労働大臣による勧告等と併せて行われる場合もあります。 参考:厚生労働省「障害者雇用状況の報告義務および企業名公表制度」
障害者雇用を推進するための企業の取り組み
求人募集・採用でのポイント
企業が障害者雇用を推進するためには、まず求人募集・採用活動を見直すことが重要です。求人票には仕事内容や勤務時間、職場環境などを具体的に明記し、障害の種類や程度に応じて配慮可能な事項を記載します。また、ハローワークや民間職業紹介事業者、障害者就業・生活支援センターなどと連携することで、マッチングの精度向上や情報発信強化が期待できます。 選考時には、筆記試験や面接方法を柔軟にし、障害特性に合わせた合理的配慮(面接時の筆談や時間延長、バリアフリールートの確保等)を行い、公平な機会を提供することが求められます。採用後も、OJTや定期的な面談を設けて職場定着を支援する取り組みが大切です。 参照:厚生労働省「障害者雇用のために事業主ができること」
職場環境整備や合理的配慮
障害者が安心して働ける職場環境の整備は欠かせません。物理的なバリアフリー(エレベーターやスロープ、障害者用トイレの設置など)だけでなく、ICT機器や補助具の導入、業務フローの見直しも効果的です。また、就業時間の調整や体調にあわせた業務分担といった合理的配慮を講じることで、雇用の定着率が向上します。 さらに、障害の有無にかかわらず働きやすい職場風土づくりも重要です。社員向けの障害理解研修や、サポーター制度(ジョブコーチの配置等)の導入により、相互理解と支援体制を強化できます。
| 整備内容 | 具体的施策例 |
| 物理的バリアフリー | スロープ、幅広ドア、点字ブロック、トイレ改修等 |
| 情報面での配慮 | 点字・音声資料、パソコンの読み上げソフト導入 |
| 就業面での配慮 | 勤務時間調整、業務内容の変更、サポートスタッフ配置 |
参照:厚生労働省「障害者の就労支援」
助成金や支援制度の活用方法
障害者雇用を促進する企業向けの助成金や支援制度も充実しています。例えば、ハローワークを通じて障害者を雇い入れる際によく利用されるのが「特定求職者雇用開発助成金」や、「障害者職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業」、「障害者雇用調整金」などです。 これらの支援は、雇い入れ時の初期費用(設備のバリアフリー化、職場適応訓練等)や、長期雇用のためのサポート人材配置・雇用維持費など、さまざまな局面で活用できます。制度ごとの申請要件や支給金額、手続き方法については、必ず最新の情報を各公式WEBサイトで確認しましょう。
| 制度名 | 概要 | 公式情報 |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 一定期間雇用継続した場合に、企業へ助成金を支給 | 厚生労働省詳細ページ |
| 障害者職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業 | 職場適応に向けた専門家派遣による支援を受けられる | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
| 障害者雇用調整金・報奨金 | 雇用率を超えて雇用した場合や、特定障害者雇用事業主への加算等 | 同上 |
障害者雇用で注意すべき法的・実務的ポイント
障害者雇用納付金制度と返還措置
障害者雇用納付金制度は、一定規模以上の企業に対して、法定雇用率を下回る場合に納付金が課される仕組みです。2025年4月以降、納付金制度の対象となる事業主規模も「従業員101人以上」に引き下げられます(現行は201人以上)。この制度の主な目的は、障害者雇用の公平性を保ち、企業全体で雇用を促進することにあります。
| 対象事業主規模 | 徴収される納付金額(1人/月) | 返還措置 |
| 101人以上 | 50,000円 | 超過雇用で調整金等の支給対象 |
法定雇用率を超えて障害者を雇用した企業には、一定額の「調整金・報奨金」が支給される場合もあります。納付金や調整金の詳しい算定方法や最新の適用範囲については厚生労働省の公式資料を参照してください。
雇用管理・就業支援の実践例
障害者雇用を実施する際は、採用から職場定着まで、法令で求められる「合理的配慮」の提供が不可欠です。採用時には公平公正な選考過程を確保し、障害特性に応じた配慮(例:面接時のサポートや試験内容の調整)を行う必要があります。 また、雇用後は、業務内容の調整や、バリアフリー化・通勤支援などの環境整備、必要に応じた支援機器の導入も重要です。合理的配慮の提供に関しては、厚生労働省の「障害者の法定雇用率制度について」が参考となります。 この他、「短時間勤務」や「在宅勤務」など多様な勤務形態の導入も柔軟に行うことが求められています。2021年改正で、精神障害者の雇用義務化が完全施行されており、雇用管理の工夫も一段と重要です(厚生労働省)。
合理的配慮の実施に関する注意点
障害者差別解消法および障害者雇用促進法により、企業には職場での合理的配慮が義務付けられています。合理的配慮とは、障害のある労働者が本来の力を発揮できるようにするために、業務内容や勤務時間、設備面などを個別事情に応じて調整することです。 配慮内容に関して、本人と企業双方で意見を擦り合わせたうえで、過重な負担とならない範囲で調整することが求められます。合理的配慮の例としては、物理的バリアフリーの整備、IT機器の導入、時差出勤や在宅勤務設定などがあります。また、意思疎通支援として手話通訳の配置等も有効です。 過度な負担に該当しない限り、配慮を怠ると法令違反となる可能性があるため、都度、詳細は厚生労働省のガイダンス(障害者雇用における合理的配慮)等で最新の実務や事例を確認しましょう。
よくある質問と誤解しやすいポイント
障害者雇用を進める際、多くの企業担当者や求職者が疑問を感じたり、誤解しやすいポイントがあります。ここでは、実際によく寄せられる質問や誤りがちな点について、最新の法令やガイドラインに基づき詳しく解説します。
精神障害者・発達障害者の雇用について
近年、障害者雇用の対象として精神障害者や発達障害者の割合が増加していますが、「精神障害や発達障害の場合も法定雇用率に算入されるのか?」という質問が多くなっています。 結論として、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)や発達障害者も、身体障害者や知的障害者同様に、雇用率算定の対象となります。平成30年から精神障害者も法定雇用率算定の対象となり、その活用は年々増えています。ただし、障害の特性を十分に理解し、合理的配慮や就労支援体制の整備が求められます。 参考:厚生労働省「精神障害者の雇用の促進等について」(2023年4月)
短時間労働者や在宅勤務に関する疑問
次に、「短時間勤務の従業員や在宅勤務の障害者も雇用率にカウントできるのか?」という質問があります。実際、就業形態が多様化する中でこの点は特に関心が高くなっています。
| 対象者 | 雇用率算定方法 | 注意点 |
| 週30時間以上 | 1人として算入 | 正社員・フルタイムパート含む |
| 週20時間以上30時間未満 | 0.5人として算入 | 雇用契約書等による明示が必要 |
| 在宅勤務等 | 勤務実態・雇用契約次第で上記該当 | 仕事の管理体制や支援策が求められる |
在宅勤務やテレワークであっても、週所定労働時間が20時間以上であれば法定雇用率の計算対象となります。短時間労働者については「0.5人」として計算されるので、人数のカウント方法に注意しましょう。 参考:厚生労働省「障害者雇用のルールQ&A(令和5年4月)」
雇用しづらい障害種別に対する配慮義務
「身体障害者に比べて精神障害者や発達障害者は雇用が難しいため、法定雇用率に算入しなくてもよいのでは?」という誤解も散見されます。 しかし、法定雇用率達成のためには、法で定められた障害者全体のうち、身体・知的・精神障害者すべてについてカウントが可能です。個々の障害の特性に応じて合理的配慮を行うことが義務づけられているため、採用後の職場環境整備やサポート体制の構築が重要です。 参考:厚生労働省「合理的配慮指針」
合理的配慮の範囲に関する誤解
「合理的配慮」と「過度な負担」の区別が曖昧になりやすいですが、事業主には障害者に対して合理的配慮を講じる法的義務があります。ただし、事業の性質や規模に照らして過度な負担が生じる場合には、配慮義務の範囲が限定されます。合理的配慮の判断は、障害当事者との対話(対話的プロセス)を重視しながら、個別具体的に検討する必要があります。 参考:厚生労働省「障害者差別解消法に係る合理的配慮指針」
障害者手帳の取得がない場合の扱い
「障害者手帳がなくても障害者雇用としてカウントできるか?」という疑問も少なくありません。原則として、障害者雇用促進法上の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)として法定雇用率の対象となるには、障害者手帳の所持が必要です。診断書のみではカウントできない点に注意が必要です。 例外的に一部認定制度があるものの、必ず証明書類を確認し、正確な雇用管理を行うことが求められます。 参考:厚生労働省「障害者雇用率制度に関するよくある質問」
障害者雇用納付金制度への誤解
法定雇用率を満たせなかった場合の「障害者雇用納付金」について、「必ず高額な納付金が必要」と誤解されることがありますが、現行制度では常用労働者101人以上の企業が対象です。また、逆に雇用率を上回る場合には調整金や報奨金が給付される仕組みも導入されています。ただし、今後法改正で基準が見直される可能性もあるため、定期的な情報確認が重要です。 参考:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度」
その他、実務でよくあるQ&A
| 質問 | 回答 |
| 障害者の解雇はできないのか? | 解雇は一般労働者と同様の基準で可能だが、特定の障害を理由とした差別解雇は禁止。合理的配慮の提供や就業支援が先に求められる。 |
| 障害の種類や程度に応じた配属の決定は? | 本人の希望と障害特性に応じ、適材適所に配属する。その際も対話を通じた決定が必要。 |
| 短期間の雇用や派遣でも雇用率対象か? | 直接雇用で週20時間以上かつ一定期間以上であれば対象。派遣の場合は、実際の雇用主(派遣元・派遣先)によってカウント先が異なるので要注意。 |
| 障害者採用後に障害の内容が変わった場合は? | 障害種別や程度の変更は各種手続・再評価が必要。最新の手帳情報で管理する。 |
このように、障害者雇用に関しては、法的要件だけに留まらず、企業実務としても多角的な視点と正確な知識が必要となります。最新のガイドラインや制度の変更動向に必ず目を通しましょう。
まとめ
障害者雇用義務化は「障害者雇用促進法」に基づき、すべての企業が義務を果たすことが重要です。2025年に法定雇用率がさらに引き上げられるため、未達成による企業名公表や罰則リスクを回避するには早めの体制整備が不可欠です。法改正の最新動向を押さえ、公的支援も活用しながら、安定した障害者雇用を推進しましょう。 ファーマーズマーケットは「最短3週間で実現する本格的農業を通じた障がい者雇用」をモットーに企業の障がい者雇用を実現すると同時に、本格的農業事業立ち上げをサポートし、黒字化まで加速させる国内唯一のサービスです。 障がい者の雇用でお困りの方は、お気軽にご相談ください。